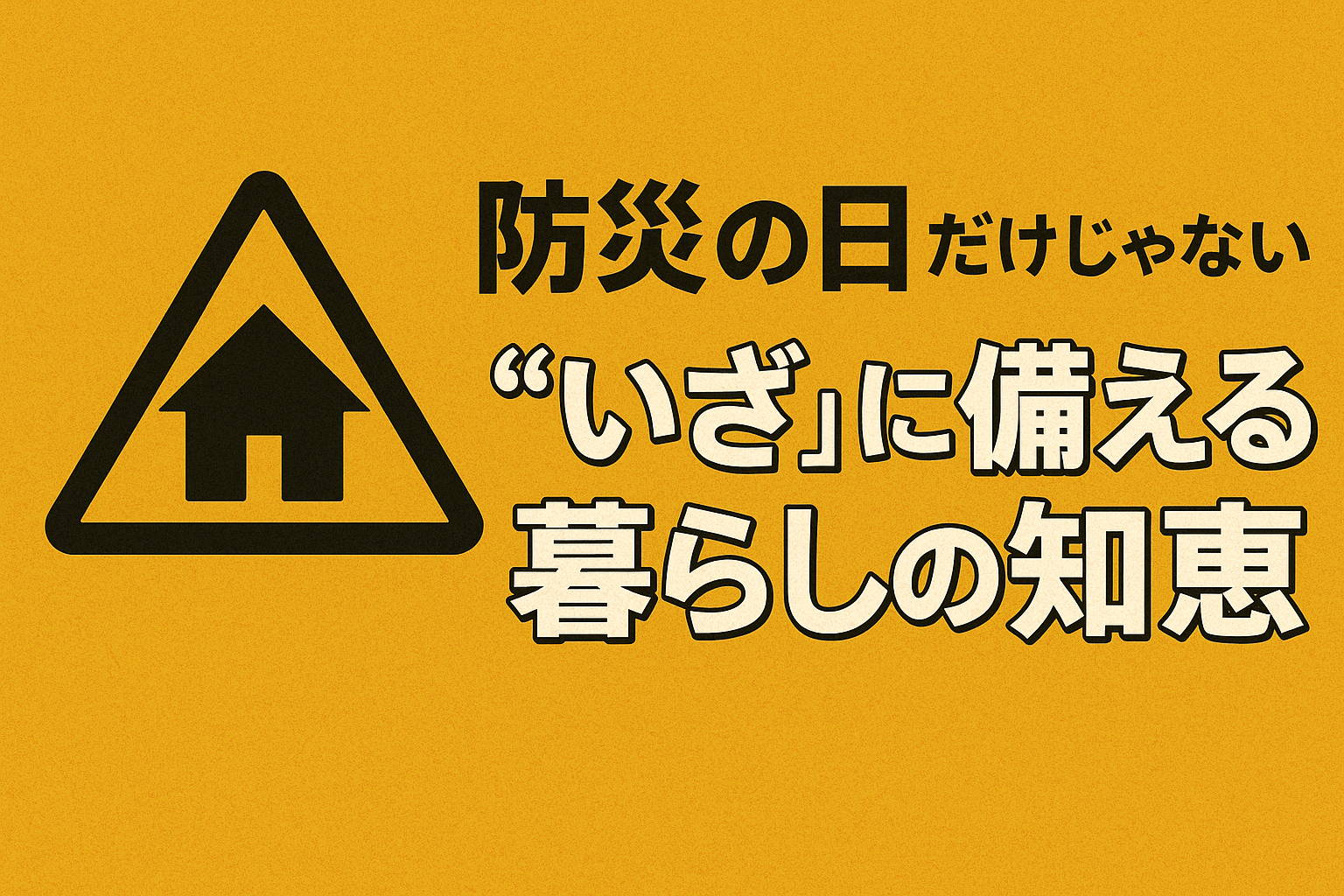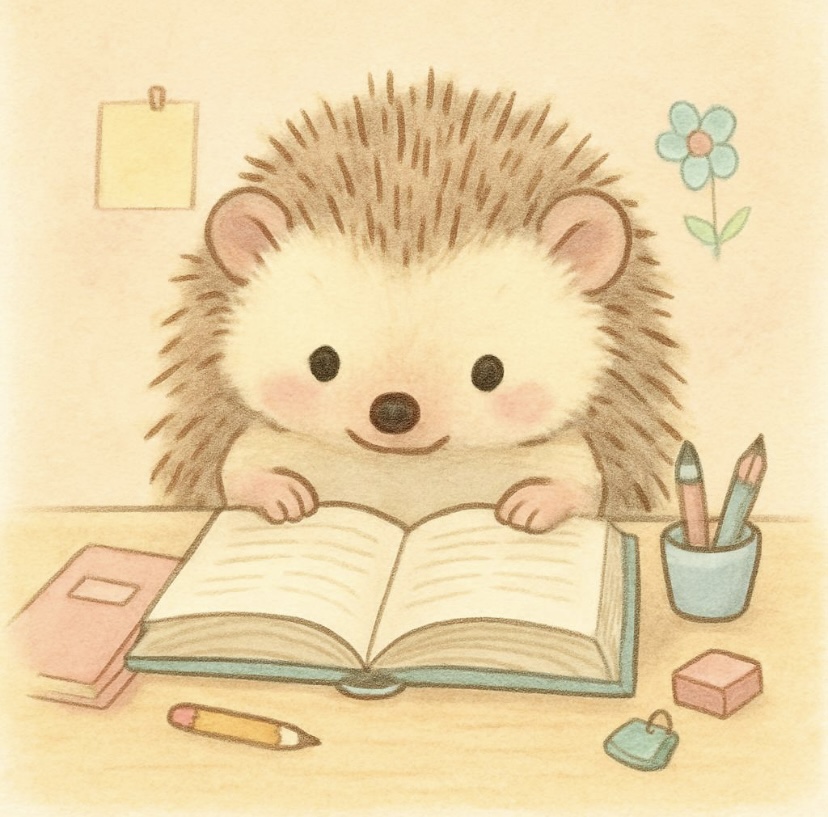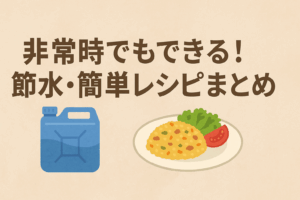「備え」は特別なことじゃない
9月1日の「防災の日」や大きな地震が起きたときだけ、急に防災意識が高まる──そんな経験はありませんか?
けれど実際のところ、防災は“イベント”ではなく、“日常の習慣”として続けることが何より大切です。
日本は地震・台風・豪雨など、自然災害が多い国。備えを一度したからといって安心はできません。しかし、「無理せず・継続的に」防災を意識する工夫を取り入れることで、暮らしの中に自然と安心が根づきます。
この記事では、「防災の日じゃなくてもできる」実践的な知恵を紹介していきます。
1. まずは“3日分”から始めよう
いざというときに最も困るのが、ライフラインの停止です。
電気・水道・ガス・通信が止まった場合に備え、まずは「3日間を乗り切る」準備を目安にしましょう。
▪ 飲料水
1人あたり 1日3リットル×3日分=9リットル が目安です。
家族の人数に合わせて、ペットボトルやウォーターサーバーの水を常にストックしておくと安心です。
また、賞味期限が切れる前に日常で使い、使った分を買い足す「ローリングストック法」が続けやすくおすすめ。
▪ 食料
缶詰・レトルト食品・クラッカー・カップ麺など、火や水が少なくても食べられるものを常備しましょう。
最近は「おいしい防災食」も増えています。例えば、五目ごはんやカレー、パンの缶詰など、非常時でも気持ちが少し落ち着く味が選べます。
▪ 生活用品
懐中電灯、モバイルバッテリー、カセットコンロ、簡易トイレ、ウェットティッシュなど。
これらを“防災袋”にまとめ、玄関や寝室など取り出しやすい場所に置いておくと、慌てずに行動できます。
2. 普段使いできる“防災グッズ”を選ぶ
防災用品というと、押入れの奥に眠ってしまいがちですよね。
しかし「普段も使えるアイテム」を選べば、日常と防災を自然に融合できます。
たとえば──
- モバイルバッテリー:普段のスマホ充電にも使える
- ソーラーライト:庭やベランダの照明として活用可能
- ポータブル電源:キャンプやアウトドアにも便利
- ブランケット:冬の膝掛けにも使える
- 保存食:お弁当やおやつとして消費できる
こうして「普段から使いながら備える」ことが、最も現実的で続けやすい防災の形です。
使った分を補充しておけば、知らず知らずのうちに備蓄が回転していく。
この“循環する防災”こそ、ローリングストックの真髄です。
3. 家の中を“安全に整える”
防災=モノの備蓄、と思われがちですが、実は家の環境を整えることも重要です。
地震のとき、家具の転倒やガラスの飛散がケガの原因になることが多いため、次の3点をチェックしてみましょう。
▪ 家具の固定
背の高い棚やタンスは、壁に固定する器具を取りつけましょう。
100円ショップでも簡易タイプの固定具が手に入ります。寝室や子ども部屋は特に優先を。
▪ ガラスの保護
窓ガラスや食器棚のガラス面に「飛散防止フィルム」を貼るだけでも大きな違いがあります。
万一割れても破片が飛び散りにくく、避難の妨げになりません。
▪ 照明・避難経路の確認
停電時に真っ暗になると、パニックになりやすいもの。
足元照明や懐中電灯を寝室・廊下・玄関などに置いておくと安心です。
また、家族で「どのルートで外へ出るか」を話し合っておくのもポイント。
4. 情報を「正しく受け取る」準備
非常時には情報の質が命を左右します。SNSのデマや古い情報に惑わされないよう、信頼できる情報源を事前に登録しておきましょう。
- 気象庁防災情報センター
- NHKニュース防災アプリ
- Yahoo!防災速報アプリ
- 各自治体の防災メールやX(旧Twitter)アカウント
スマホの「緊急速報」は音が大きく驚きますが、命を守るための重要な通知です。常にONにしておきましょう。
5. 家族・職場で「共有」しておく
どんなに完璧に備えても、情報が家族で共有されていなければ意味がありません。
家族全員で「いざというときの行動ルール」を確認しておきましょう。
▪ 家族間の連絡方法
携帯電話が繋がらない場合に備え、災害用伝言ダイヤル(171)やLINEの災害時連絡サービスを練習しておくのがおすすめです。
▪ 集合場所・避難所
自宅近くと、職場・学校など離れた場所それぞれに「集合地点」を決めておきましょう。
自治体のハザードマップを見ながら、「水害時はこっち」「地震時はここ」とシーン別に話しておくと安心です。
▪ ペットの避難
ペットがいる家庭では、ペット可の避難所や預け先を確認しておきましょう。
普段からキャリーバッグや餌・トイレ用品をまとめておくと、慌てずに行動できます。
6. 無理なく続ける“防災習慣”
防災の最大の敵は、「面倒くさい」「そのうちやろう」という気持ちです。
完璧を目指すより、“小さな積み重ね”を続けることが何より重要です。
おすすめは、次のような月ごとの習慣リストです。
| 月 | チェック項目 |
|---|---|
| 1月 | 非常食・水の賞味期限をチェック |
| 3月 | 家具固定や避難ルートの確認 |
| 6月 | 梅雨・豪雨対策(防水グッズ・土のう) |
| 9月 | 防災の日に備蓄見直し |
| 12月 | 暖房・停電時の防寒対策を確認 |
年に数回、スマホのリマインダーなどに登録しておけば、手軽に習慣化できます。
7. 防災を「暮らしのアップデート」として楽しむ
防災というと「不安」や「恐怖」と結びつけがちですが、実は“暮らしをより快適にする工夫”でもあります。
非常食を試食してお気に入りを見つけたり、ポータブル電源でベランダキャンプを楽しんだり──。
そうした“遊びの延長”で備えることが、結果的に防災力を高める近道です。
「備える=安心をデザインすること」。
そう考えると、防災は決して堅苦しいものではありません。
まとめ:小さな備えが、大きな安心に
防災は「特別な日」ではなく、「今日からできる暮らし方の一部」。
水を1本多めに買う、ライトを玄関に置く、アプリを1つ入れる。
そんな小さな行動が、いざというときに命を守る大きな力になります。
忙しい日々の中でも、「続けられる備え」を意識することで、心の余裕も生まれます。
あなたの“今日からの一歩”が、家族を、そして自分を守る力になります。